【旅行記】西肥バス・生月バスで巡る佐世保・平戸旅~北松浦半島を周回し旅を締めくくる~
前話
西肥バスと生月バスで巡る佐世保・平戸エリアのバス旅も、いよいよ2日目の後半に突入。午前中は西肥バスの吉井・世知原線に乗車したのち、瀬川汽船の航路とさいかい交通・西肥バスの路線を乗り継ぎ、西海橋を訪ねた。午後は再び佐世保市から北へ向かい、佐世保駅前を起点に松浦駅前、平戸桟橋を経由して再び佐世保駅前へ戻る周回ルートで3路線を乗り継ぎ、今回の旅を締めくくった。
佐世保バスターミナルから松浦駅前行きに乗車

西海橋西口から佐世保駅に戻り、駅前の佐世保バスセンターへ。次に乗車するバスは、このバスセンターが始発だった。西肥バスのターミナルである佐世保バスセンターは、福岡・長崎・長崎空港への高速・特急バスと一部の路線バスが発着する。今では珍しくなった頭端式のターミナルで、バスはバックして発車していく。高速・空港バスがメインで使う施設だが、広域運行される路線バスの一部も始発・終点となっている。ここから発車するのは伊万里・嬉野・松浦・平戸方面へ向かう各路線のバス。佐世保駅前が始発地の場合のみバスセンターから発車し、一部路線で設定されている佐世保総合医療センター入口始発便はバスセンターには乗り入れない。また、いずれの路線もバスセンターを出たあとに佐世保駅前のバス停にも停車する。
ここからは3本のバスを乗り継ぎ、再び北松浦半島を巡っていく。最初に乗車するのは松浦駅前行きのバス。松浦市は北松浦半島の北側にあり、平戸市と佐賀県伊万里市の間に位置する。松浦鉄道西九州線も松浦を経由するが、半島を周回するためやや遠回りとなる。路線バスのほうが一部区間をショートカットして走るので所要時間が短く、この区間では基本的にバスを使う方が一般的である。ちなみに、路線バスの所要時間は約1時間10分に対し、鉄道はおよそ1時間45分〜2時間かかる。半島の北側に位置するため、佐々経由も有田経由も所要時間に大差はない。
この路線は、後ほど乗車する平戸発着の半急行バスと途中までまったく同じ経路を進む。佐世保市街から吉井までの区間では、半急行バスが急行運転を行う一方で、松浦線は全てのバス停に停車する。要するに各停便の役割を担っている。朝の時間帯には、時刻表上で各停の松浦線を半急行が追い抜く場合もあるが、日中は運行間隔が空くため、先に出た方が先に着く。佐世保~松浦間のバスは、多くの時間帯で1時間に1本の運転となっており、平戸発着の半急行バスと合わせると、佐世保〜吉井(田の元)間では毎時1〜2本の運転となっている。
乗車記録 No.15
西肥バス 佐世保-松浦線 松浦駅前行
佐世保バスセンター→松浦駅前

佐世保バスセンターでは、自分のほかにもう1人が乗車。バックして発車後、佐世保駅前バス停に停車すると、ここで7~8人の乗車があった。日中ということで、特に大野以降ではバスの本数が少なくなることもあってか乗ってくる乗客も想像以上に多かった。ここからバスは佐々市街まで、一貫して国道204号を走っていく。大野までの区間は、この日の午前中に世知原経由のバスで通った道を戻る形となる。佐世保市街地の途中のバス停でも比較的多くの乗車があり、佐世保市役所前を出る頃にはほぼ満席に。夏休みということもあり、沿線から佐世保に出てきていた小学生の利用が多かった。

バスは大野を通過後も国道204号線を進んでいく。このあたりは松浦鉄道沿いに旧道が通っており、そちらにも路線バスが走っているが、松浦・平戸方面のバスは国道のバイパスを進む。以前は乗車中の松浦行のバスも旧道を経由していたらしい。現在、旧道経由バスは相浦・佐々発着で運転されている。こちらも気になるので、次に佐世保を訪れた際には乗車してみたい。吉岡団地など途中のバス停で乗客がどんどん下車し、バイパス山本を出る頃には車内の混雑もひと段落した。松浦鉄道はここから相浦を経由するが、国道204号はショートカットして佐々へ向かっていった。

やがて佐々の市街地へと入ると、一旦国道204号線を離脱して交差点を左折。佐々中央バス停を経由して、佐々バスセンターに到着。1日目に松浦鉄道から西肥バスの楠泊線に乗り換えた佐々バスセンターに、1日ぶりに帰ってきたことになった。その後は佐々役場前を経由して、再び国道204号線へ。市街地の各バス停で乗り降りがあり、乗客の一部が入れ替わった。

その後、バスは佐々川を渡る新佐々橋を通過し、川沿いを北上していく。途中の小春というバス停は、近くにある県立清峰高校の最寄りバス停。ここでは部活帰りらしき高校生が数人乗り込んできた。松浦鉄道にも清峰高校前駅が設置されているが、松浦方面からの通学には基本的に路線バスが使われているのだと思う。乗車した高校生たちも松浦の市街地まで乗車していた。ちなみに、この清峰高校は2009年春の選抜高校野球で花巻東を破り、優勝した経験をもつ。その時ピッチャーだった今村猛投手は、その後広島東洋カープにドラフト指名され、2021年まで活躍した。

佐々を出ると、次は朝に訪ねた吉井の街へ。バスは佐々川に沿って進み、朝に世知原経由のバスに乗り込んだ吉井バス停を通過した。佐世保市街地から乗車した乗客は、ほぼ全員が吉井までのバス停で下車していき、車内は途中から乗り込んだ乗客数人だけに。吉井を通過後も、あと少しだけ国道204号線を進んだ後、田の元バス停の先にある松浦鉄道トンネル上の交差点で右折し、松浦方面へ進んだ。
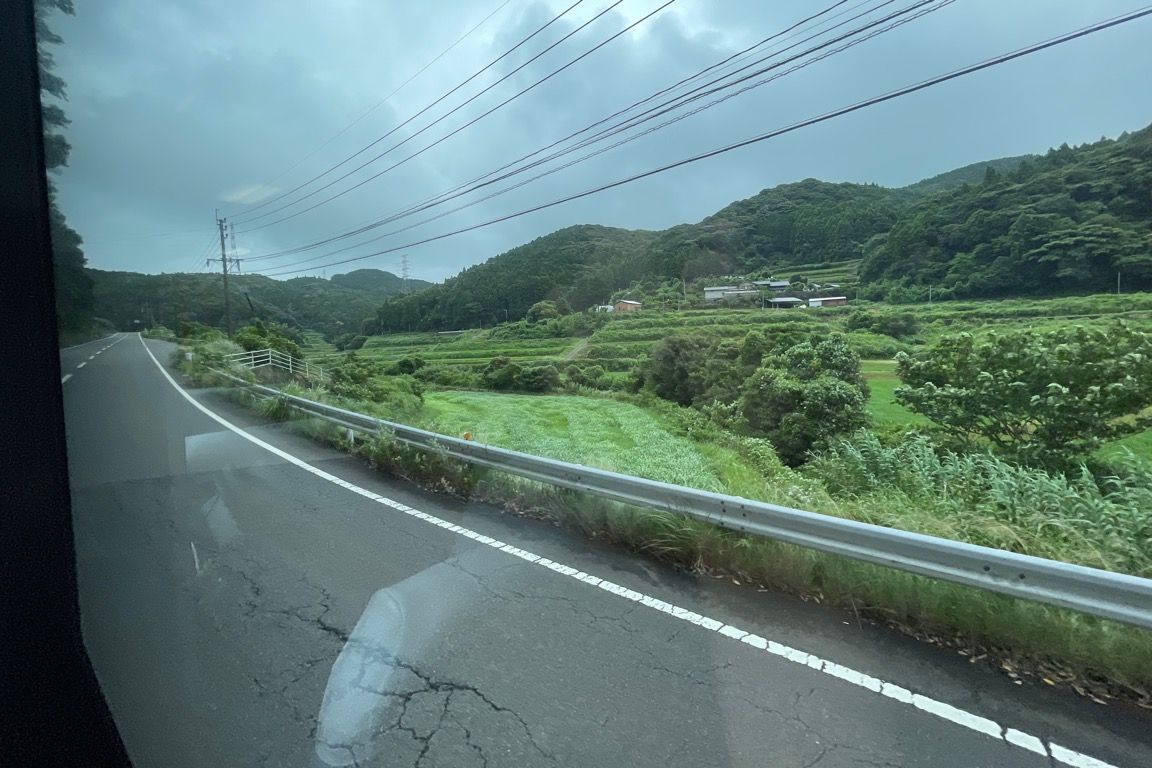
バスは松原の集落を通過し、その後県道40号線へ。旧道から県道へと入る際、車窓には松浦鉄道の立派なコンクリートのアーチ橋が見えていた。バスはここから福井という地区を通り、福井峠を越えて松浦市街へ進んでいく。将来的には西九州道が開通予定だが、現状では松浦~佐世保間の最速経路である。現在も福井峠・妙観寺峠を貫くトンネルで直線的に松浦から皆瀬まで移動できるため、おそらく西九州道が開通しても、所要時間は大きく変わらないのではないかと思う。

緩やかな坂を上り、のどかな車窓が広がる福井地区を縦断すると、バスはやがて福井トンネルへ。このトンネルの途中で佐世保市から松浦市へと入った。トンネルを抜けると、そこからは下り坂で松浦市街を目指す。朝に乗車した知見寺越えほどではないが、こちらもいつの間にかかなり標高を上げていたようで、車窓には谷や棚田が広がった。坂を下り続けると、ほどなくして奥に松浦市街が見え始める。バスは志佐川と合流したのち、交差点を右折して松浦市の市街地中心部へ。まもなく終点の松浦駅前に到着した。
松浦駅で小休憩、平戸桟橋行きに乗り換える

バスの終点・松浦駅前に到着。松浦鉄道の列車で通過したことはあったが、松浦市に降り立つのは今回が初めてだった。松浦は周囲を山と海に囲まれたのどかな街で、漁業が盛ん。中でもアジの水揚げ量が多く、街は自ら「アジフライの聖地」を宣言している。松浦市にはいくつかの離島があり、このうち福島と鷹島の2つの島は九州本島と橋で結ばれている。しかし、最寄りの九州本島が佐賀県唐津市および伊万里市のため、松浦市街へ陸路で移動するには一旦佐賀県を経由しなければならないというちょっと面白い現象が発生している(なお、松浦市街に近い今福・福島口へは渡船がある)。
一時期送電線が好きだった筆者にとって、松浦は「発電の街」という印象も強い。市内には九州電力の松浦発電所と、電源開発(J-POWER)の松浦火力発電所という大きな火力発電所がある。いずれも九州内の電力供給を担う重要な施設で、ここから伸びる送電線は九州島内を縦横に結ぶ幹線系統へ接続されている。九州自動車道の基山PA付近で高速道路をまたぐあの巨大な送電線をたどれば、その一端はこの街につながっている。
松浦駅前では約40分の乗り継ぎで平戸桟橋行きに乗り換えた。松浦鉄道にとっては主要駅の一つであり、駅舎は「松浦交通センター」の愛称がある。駅舎内には待合室とまつうら観光物産協会の窓口がある。松浦鉄道、西肥バスそれぞれが業務委託を行っているため、窓口では鉄道・バス両方のきっぷを取り扱っている。駅舎とホームは独立しており、改札はないためホームへは自由に出入りができる。駅舎の横には西肥バスの駐車場があり、駅前ロータリーにはベスト電器松浦店があった。松浦市の人口は2万人ほど。長崎県の市としては最も人口が少ない。

駅の裏手には工場のほか、ドラッグストアやスーパー、それに松浦市の文化会館などがある。構内踏切を渡って駅の裏側へ行くことができるが、跨線橋も用意されていて、こちらからは駅周辺を一望することができた。海側では西九州道の建設が進んでいた。現在佐々ICから松浦ICまでの区間が事業中。このうち江迎鹿町ICから松浦IC間は今年度中の開通が予定されている。
やがて松浦鉄道の列車がやってくる時間になったので、少し見物することに。しかし到着時刻を過ぎても現れず、しばらくすると佐世保方面の出発信号機下に設置された電話応答を促す表示灯が点滅し始めた。どうやら少し遅れているらしい。しばらく待っていると、約6分遅れで列車が到着。松浦駅では本来少し停車する予定だったが、遅延のためすぐに発車していった。なお、ここから伊万里方面へは西肥バスの路線もあったが、今年3月に廃止され、現在ここから伊万里へは松浦鉄道が唯一の移動手段となっている。この他、以前の松浦駅前からは世知原へ向かうバスも発着していたが、こちらも現在は廃止されている。
松浦鉄道と並走し平戸島へ渡る平戸桟橋行に乗車

さて、松浦駅で小休憩の後、今度はここ始発の平戸桟橋行きに乗車した。松浦-平戸線は、松浦鉄道と並走して平戸口方面へ進み、そこから平戸大橋を渡って松浦市と平戸市の両市街を結んでいる。かつては伊万里-平戸間を結ぶバスとして運行されていた歴史を持ち、松浦で系統が区切られた後も、最近まで本数が比較的多い路線だったが、今年3月のダイヤ改正で運行本数が大幅に削減となり、今では平日わずか2往復のみの運行となっている。松浦市と平戸市を結ぶ路線でありながら、この路線が今回の旅で乗車する路線の中でも、最も運行本数が少ない路線だった。平戸から松浦へは朝と夕方に1本ずつ、松浦から平戸へは朝と午後の早い時間に1本ずつの運行となっている。時刻から推測するに、平戸方面へは通学需要、松浦方面へは通院や買い物など日中の移動需要を担っている。この便は平戸方面行きとしてはその日の最終便だった。
下調べの段階でわかってはいたが、この次に乗るバスは、先ほど佐世保から松浦へ乗車した車両と同じだった。こうしたケースは地方路線では珍しくないが、運転士さんにとても申し訳なくなってしまう。松浦駅前からの乗客は自分を含めて3人。本数は減ってしまったものの、今も利用者は一定数いるようだった。
乗車記録 No.16
西肥バス 松浦-平戸線 平戸桟橋行
松浦駅前→平戸桟橋

松浦駅前を発車すると、バスはすぐに交差点を右折して国道204号線へ。ちなみに交差点の角にあるホテルは、今回の旅程を組む際、鹿町のホテルとどちらに泊まるか迷った場所だった。バスは志佐川を渡って松浦鉄道の線路をくぐり、やがて海沿いのバイパスと合流。道の駅松浦の前を通過し、松浦の市街地を後にした。

やがて車窓には巨大な発電所の施設群が現れる。松浦鉄道と国道204号線はこの先、電源開発(J-POWER)と九州電力の火力発電所の前を通過する。先ほどまでの港町らしいのどかな景色から一転、無骨な煙突や設備が並ぶ工業地帯の光景となる。九州電力の発電所の正門前には松浦発電所前駅と松浦発電所バス停があり、その上空を太い送電線が横切る。西九州変電所へ続く「松浦火力線」は500kVという超高圧送電線で、長く連なる碍子がその規模を物語る。松浦駅前から乗った他の乗客は発電所前後の停留所で下車し、車内は早くも自分1人だけとなった。

その後もバスは国道を淡々と進んでいく。難読地名として知られる御厨(みくりや)は、松浦市の離島・鷹島への渡船が発着する場所。このあたりで一瞬だけ海が姿を見せるが、それ以降、田平港までは海からやや内陸に入るため、車窓は田畑や森が中心となる。木場地区を経由しながら、バスは田平エリアへと近づいていった。

やがて平戸市の田平支所前を通過すると、バスはたびら平戸口駅付近へ差し掛かる。1日目に乗車した平戸高校前行きのバスは駅前広場に入ったが、この便は駅舎前へ立ち寄らず、国道上の「平戸口駅前」停留所に停車するのみとなる。沿道に住宅や商店が密集するなかを進み、田平港に停車すると、ここでは1人の乗車があり、しばらく続いた貸切状態がここでようやく解消された。

田平港を出ると、いよいよこの路線のハイライト、平戸大橋の区間へ入る。2日連続でこの橋を渡って再び平戸島へ。バスの車内は静かで、エンジン音と橋を渡る風の音だけが響いていた。橋を渡り切ると、ゆるやかな坂を下って市街地へ。田平港で乗車した乗客は猶興館高校前で降りていき、終点・平戸桟橋には定刻通り到着。2便連続でお世話になった運転士さんに改めてお礼を告げてバスを下車した。

2日続けて訪れることになった平戸桟橋。この日もここでおよそ40分の乗り継ぎ時間があった。前日は海沿いを歩いてオランダ商館方面へ足を延ばしたが、この日は英国商館通りを歩いて、市街地の方まで歩いてみた。異国情緒と昔ながらの日本の街が共存する平戸の街。何をするでもなく歩くのも楽しい。
桟橋前の海は、昨日の穏やかさとは打って変わり、時おり強まる風を受けて細かな波を立てていた。頭上には灰色の雲が流れ、通り過ぎるたびに雨脚が一瞬強まる。その合間に差す湿った空気がまとわりつき、汗がにじむような蒸し暑さに包まれた。移り気な空模様もまた、盛夏らしい旅の一場面である。
平戸桟橋から半急行を乗り通し、旅を締めくくる

さて、いよいよ今回のバス旅も終盤。次に乗る平戸桟橋発の佐世保駅前行き半急行が、路線バスとしては最後の乗車となった。ここから終点の佐世保駅前(バスセンター)まで、およそ1時間半の道のり。これを乗り通し、今回の旅を締めくくる。
佐世保と北松浦半島各地、そして平戸島を結ぶ「佐世保-平戸線」は、この地域を走るバスの中でも基幹路線であり、平戸島への代表的なアクセス手段である。今回の旅では、初日に江迎-平戸桟橋間や田平港-江迎間、さらにこの日の朝には江迎-吉井間と、断片的に乗っていたが、最後はこの路線を全区間通しで乗ってみることにした。こうして一本のバスで全区間を乗り通すことで、その路線の持つ役割や距離感を改めて見てみたいと思う。かつてはハイデッカー車両が投入されていたこともあるそうだが、現在は一般的な路線バスタイプの車両で運行されている。景色を楽しみつつも、少し長丁場の移動になる。
この路線の大きな特徴は、吉井から佐世保市街地側の区間で急行運転を行うこと。平戸桟橋から吉井までは各停で、吉井から先は主要停留所のみ停車する「急行」に切り替わる。基本的にこういう場合の種別は「区間急行」と呼ぶ場合が多いが、西肥バスではより直感的に「半急行(略して半急)」という種別を設定している。この半急行は全国的にもこの路線でしか見ることのできない種別となっている。急行区間では、同じ道を走る松浦-佐世保線のバスが各停として運行しており、利便性を補完し合っている。
運行本数は上りが14本、下りが13本の計13.5往復。概ね1時間に1本程度だが、朝の時間帯は上り便が1時間に2本とやや多めに設定され、その分日中は間隔が開く。かつてはもう少し本数も多かったが、近年は利用者減少の影響もあり徐々に減便されている。
乗車記録 No.17
西肥バス 佐世保-平戸線 [半急]佐世保バスセンター行
平戸桟橋→佐世保バスセンター

平戸桟橋から田平港までは、直前に乗車した松浦~平戸線で通った道を戻る形となる。これでこの区間を走るのも4度目となり、景色もすっかり見慣れてきた。平戸桟橋では、自分のほかにもう1人が乗車。さらに平戸新町では5人、猶興館高校前でも2人が乗り込み、車内は少し賑わいを見せた。
やがて、この旅最後となる平戸大橋を渡り、平戸島と別れを告げる。今回は平戸城や教会を見学する時間が取れなかったため、次回はもう少しゆったり観光する時間を設けたいと思いつつ、バスの車窓から平戸大橋を眺めていた。
平戸島内では晴れ間も見えていたが、九州本島側へ戻り、田平港付近を通るころには一時的に土砂降りの雨となった。田平港では観光客らしき2人が下車。このころには天気は回復しつつあったものの、まだ所々に雨雲が残っており、時折雨脚が強まることもあった。平戸大橋東口バス停では、近くのスーパーへ買い物に向かう客らしき数人が下車し、入れ替わりに1人が乗車した。

平戸大橋東口を出たバスは、そこから江迎、吉井を経由して佐々へ向けて走っていく。江迎までは1日目に、江迎から吉井までは朝に乗車した区間ということで景色自体は既に眺めた区間となる。しかし、時間帯や天気が変わると景色の印象も微妙に異なるのが面白い。午前中は雨に煙っていた山々も、午後の光に照らされて少しずつ表情を変え、緑がいっそう鮮やかに映えていた。
バスはしばらく山間部を走り、峠を越えて坂道を下る。途やがて進行方向の右側に江迎湾が見えてくると、バスは江迎の街へ。江迎ではまた数人が下車して行き、また乗客が入れ替わる。平日のこの時間に乗り通す人は決して多くはない。

江迎の街を離れると、バスは再び山間の景色の中を進んでいく。松浦鉄道も、乗車中のバスも、江迎川や佐々川の谷間に沿って走るため、蛇行しながら少し遠回りしながら佐世保へ向かっていく。江迎から佐々へは山中を抜ける県道227号線、吉井から皆瀬へは県道40号のバイパスといったショートカット道路があり、マイカーで移動するならおそらくどちらかを経由するのが一般的なのだと思う。
吉井の少し手前、田の元付近では松浦市街から福井峠を越えてきた県道40号線と合流する。ここからは、先ほど乗車した佐世保―松浦線と同じルートを辿り、佐世保駅を目指していく。

バスは朝に立ち寄った吉井へ差し掛かる。ここでバスは急行運転へと入った。走る道は先ほど乗車した佐世保-松浦線と同じだが、ここから先は一部のバス停にしか停車しない。所要時間は大きくは変わらないものの、こまめな停車が少ない分、バスはスイスイと先へ進んで行った。
やがてバスは佐々川を渡って、佐々の市街地へ。佐々バスセンターでは数名が下車する代わりに7・8人の乗客が乗り込んできて、再び車内は賑やかに。この時間のロータリーには、数台のバスが待機していて、ようやくバスセンターらしい光景を見ることができた。バスセンターを発車すると、次は佐々新町に停車する。市街地の中にある佐々中央バス停も通過するところが急行運転らしかった。

佐々バスセンターを出て国道204号線へ戻ると、その後はひたすら佐世保駅前を目指して走っていく。真申入口を経て本山トンネルを抜けると、松浦鉄道の線路を跨ぎ、バイパスを東へと進んだ。本山を過ぎると車窓には旧道が現れる。そこにも別のバスが走っており、まるでデッドヒートのような様相を呈しながら進んだ。こちらのバスも途中の停留所で乗降が多く、旧道経由のバスと一進一退の攻防を繰り返す。最終的には信号1回分こちらが先行し、一足早く大野へ到着。ここで車内の半数以上の乗客が下車し、車内は一気に閑散とした。

大野から先は同じ道を走るバスの本数も多くなり、乗車中のバスへの乗り降りも逆に少なくなる。時刻は17時になろうとしていて、街はまもなく夕ラッシュへ突入しようとしていた。途中、堺木からは近くの高校の生徒が乗車してきたものの、それ以外の乗車はほとんどなく、バスは市街地中心部のバス停で乗客を降ろしながら進んだ。市街地中心部でも一部のバス停は通過するので、佐世保近郊を走るバスを颯爽と追い抜いていく。終点の佐世保駅前ではバスセンターへ入線。ここで乗客を降ろす。最終的に平戸から乗り通していたのは、自分ともう一人だけ。平戸-佐世保を結ぶバスであっても、利用は断片的であり、短距離利用が多いというこの路線の実情を垣間見ることができたところで、2日間に渡る路線バスの旅もこれにて終了となった。
乗車記録 No.18
西肥バス させぼ号 博多バスターミナル行
佐世保バスセンター→西鉄天神高速バスターミナル

数時間ぶりに戻ってきた佐世保バスセンターでは、1時間ほど待ち合わせたのち、高速バス「させぼ号」で福岡へ。「させぼ号」にはこれまで何回か乗車しているが、西肥バス担当便に乗車するのはこれが初めてだった。西肥バスの高速路線は長崎線に乗車経験がある。長崎線は西肥カラーの車両が使われるが、させぼ号には「Highway Express」と書かれた専用塗装車が使用されている。乗車したバスは、佐世保市街の渋滞で多少遅れたものの、その後は快調に西九州道、長崎道、九州道、福岡都市高速を経由して福岡へ。西鉄天神高速バスターミナルでバスを下車して、今回の旅を終えた。
おわりに
今回の旅では、3年ぶりに九州を路線バスで巡り、佐世保・平戸方面へ足を延ばした。ここしばらく遠出の旅が続いていたこともあり、久しぶりの九州旅はかえって新鮮で、近場だからこそ味わえる旅の楽しさを改めて実感できた。
特に今回初めて訪れた平戸は、九州に暮らしながら未踏だった地である。旅を計画する中で知り、行くことを決めた生月島では、夏らしい島の景色に心を奪われ、まだまだ知らない九州の魅力が数多く残されていることを実感した。九州に住んでいるからこそ楽しめるディープな旅の面白さを感じた瞬間だった。
鉄道旅とはひと味違い、バス旅は地域密着の路線バスで各地を訪ねることで、その土地に暮らす人々の生活を垣間見ながら進むことができる。鉄道が都市や主要駅を軸に地域を結ぶのに対し、バスは町の中や生活道路を通り、時には学校帰りの学生や買い物客と席を並べる。路線の一本一本がその地域の暮らしと直結しているからこそ、観光地だけでは見えない素顔の九州に触れられる。それこそがバス旅の面白さであり、より生活に近い目線で地域を味わえるのが最大の魅力だと思う。
今回、西海橋から佐世保へ向かうバスに乗車したことで、過去の旅と合わせると、長崎半島先端・樺島から宮崎県の道の駅つのまでを路線バスでつないだことになった。しかし、利用者減や人手不足の影響から、九州でも路線バス網の縮小が進んでおり、数年前に乗車した路線も廃止されてしまった路線が少なくない。例えば堀川バスと産交バスで八女から山鹿を結ぶルートは路線の廃止・区間短縮によって成立しなくなったほか、宮崎県では都農と高鍋を結ぶ宮崎交通の路線が数年前になくなった。さらに今秋には熊本市内と松橋産交を結ぶ路線も区間短縮によって姿を消す予定で、いよいよ都市郊外でも路線再編が始まりつつある。もちろん最優先すべきは地域住民の足の確保であるが、交通ファンとしては一抹の寂しさを覚えずにはいられない。だからこそ、今残されている路線との出会いもまた一期一会。その縁を大切に旅を重ねたいと思う。
今後は数回に一度の頻度で九州を舞台に旅を企画するつもりである。まだまだ訪れたことのない土地、乗ってみたい路線は数多く残されている。次の行き先は未定だが、候補地はいくつかあり、構想を練っているところである。次の旅でも、また新たな九州の景色と出会えることを楽しみにしている。
その他の九州地方の旅行記
- 九州再発見シリーズ
- その他小旅
今回初めて乗車した路線・区間
【バス路線】
西肥バス 佐世保-伊万里線 伊万里駅前-佐世保駅前間
西肥バス 楠泊線 佐々バスセンター-江迎間
生月バス 平戸線 平戸桟橋-加勢川入口間
生月バス 平戸高校線 一部桟橋-平戸高校前間
西肥バス 平戸高校前線 平戸高校前-平戸口駅前
西肥バス 世知原・吉井線 吉井-佐世保駅前間
西肥バス 佐世保-西海橋線 西海橋西口-佐世保駅前
西肥バス 佐世保-松浦線 佐世保バスセンター-松浦駅前
西肥バス 松浦-平戸線 松浦駅前-平戸桟橋
西肥バス 佐世保-平戸線 平戸桟橋-佐世保バスセンター
【船舶航路】
瀬川汽船 佐世保港-横瀬西港